top of page
本店:9:30-18:30(水曜休)
真庭店:9:30-18:30(水曜休)
仏事のいろはと心得


数珠の房などに使われる「正絹」と「人絹」の違いって?
新入社員のシバです。 今日は、数珠の房や仏具などでよく耳にする「正絹(しょうけん)」と「人絹(じんけん)」の違いについて、基本的なところをお話しさせていただきます。 まず大きな違いは、原料が天然か人工か、という点になります。正絹は、蚕の繭から作られる天然素材の絹、いわゆるシルクが100%使われています。一方の人絹は、絹のような見た目や質感を再現するために作られた化学繊維で、主にレーヨンやアセテートといった素材が用いられています。 正絹は、本物ならではの上品な光沢と、しっとりとした風合いが大きな魅力です。房や打敷などに使われていると、落ち着きのある美しさがあり、長く大切にしたいと思わせてくれます。ただし、とてもデリケートな素材のため、水や湿気に弱く、お手入れには少し気を使う必要があります。梅雨時期などは、特に注意が必要だと教わりました。 一方、人絹は正絹に比べると扱いやすく、湿気にも比較的強いのが特徴です。見た目も最近はとてもよくできていて、ぱっと見ただけでは違いが分からないこともあります。価格を抑えたい場合や、日常的に使われる場面では、人絹が選ば
1月22日


花立は左?三具足で知っておきたい仏具の置き方
新入社員のシバです。 入社してから日々勉強の毎日で、まだまだ至らない点も多いのですが、今回は仏具の飾り方についてご紹介させていただきます。 お仏壇の飾り方というと、仏教の伝統や正式な形を思い浮かべる方も多いかと思います。たとえば「五具足(ごぐそく)」と呼ばれる、花立・香炉・燭台を左右対称に一対ずつ置く形が、基本として知られています。ただ、実は必ずしも仏具は「一対でなければならない」という決まりではないそうです。 最近では、上置仏壇や手元供養など、コンパクトなお仏壇を選ばれる方も増えてきました。そのような場合、スペースの関係で五具足をすべて置くのが難しいこともあります。そこでよく選ばれているのが、「三具足(みつぐそく)」という飾り方です。これは、花立・香炉・燭台をそれぞれ一つずつ置く形で、見た目もすっきりして、現代の暮らしにもなじみやすいように感じます。 ここで一つ、意外と迷われやすいのが花立の位置です。花立を一つだけ置く場合は、お仏壇に向かって左側に置くのが基本とされています。左右対称でなくても失礼にあたることはありませんので、安心していただいて
2025年12月30日


仏壇の「りん」ってどんな意味があるの?音を鳴らすタイミングと選び方
新入社員のシバです。 今回は、お仏壇参りのときに使う「りん(鈴)」について、基本的な意味や使い方を少しご紹介します。 りんとは、お仏壇の前で手を合わせる際に鳴らす、金属でできた仏具のひとつです。チーンと響く澄んだ音色、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。この音には、私たちの心にある邪念を払い、気持ちを整える役割があるとされています。また、故人や仏様への祈りの心を、極楽浄土へ届ける合図のような意味合いもあるそうです。 りんを鳴らすタイミングは、お経を読む前と後が基本とされています。お経の前には、これから手を合わせますという心の切り替えとして、後にはお参りが無事に終わったことをお伝えするため、と教わりました。澄んだ音がゆっくりと消えていくのを感じながら、自然と心が落ち着いてくるのも、りんの大切な役割なのかもしれません。 鳴らし方にも少しだけコツがあります。りん棒を強く打ちつけるのではなく、45度くらいの角度でやさしく当てると、きれいな音が響きやすいと言われています。試してみたのですが、角度を意識するだけでずいぶん違う音になりました。...
2025年12月21日


香典ってどうして“香”なの?意味と基本のマナーをやさしくご紹介します
新入社員のシバです。今回は、「香典(こうでん)」についてのお話です。 お葬式で当たり前のように使われている言葉ですが、実は昔の風習がそのまま名前として残っているんです。 昔は、仏様は“御香を召し上がる”という考え方がありました。 そのため、お葬式の際にはお金ではなく「御香」そのものを持参していた時代があったそうです。なんだか時代の空気が感じられて、初めて知った時は少し驚きました。 現在では、香を持参する文化は薄れましたが、”香典=香の代金”として名前だけが受け継がれています。とはいえ、意味合いは少し変化していて、いまは「ご遺族の負担を軽くする」という相互扶助の気持ちがより強いものになっています。人と人のつながりを感じる習慣だなと思います。 また、香典に入れるお札については、新札ではないほうが良いとされています。あらかじめ準備していたように見えてしまうからですね。ただ、どうしても新札しか手元にない場合は、一度軽く折って使用することもあります。 さらに、宗教によって表書きやマナーが違う点にも注意が必要です。 仏式・神式・キリスト教式では書き方や包み方
2025年12月8日


はじめての袱紗(ふくさ)選び|慶弔でのマナーと使い方のポイント
新入社員のシバです。 今日も仏事まわりで知っておくとちょっと安心できることをご紹介したいと思います。 今回は「袱紗(ふくさ)」についてです。 冠婚葬祭の場ではよく聞く言葉なのですが、意外と“ちゃんと使ったことがある人”って少ないのでは…と感じています。 まず、袱紗とはご祝儀袋や香典袋を包むための四角い布のことです。封筒が汚れたり折れたりするのを防ぐためでもありますし、相手への敬意や気持ちを丁寧に伝えるための大切なアイテムです。見た目だけでなく、振る舞いとしても大事なんだと教えてもらいました。 袱紗には大きく分けて「包むタイプ」と「挟むタイプ」があります。 包むタイプは、風呂敷のように金封を包む伝統的な形で、より丁寧な印象を与えると言われています。しっかり使いこなすと、所作まできれいに見えるのが良いところです。 一方で、挟むタイプ(金封袱紗)は、開くとポケットのようになっていてサッと挟むだけで大丈夫なので、私のような初心者でも安心して使える手軽さがあります。 色や柄にも決まりがあって、ここがちょっと迷うポイントかもしれません。 慶事では赤・朱色・金
2025年11月28日


お仏壇の「三大供養」って?花・香・灯に込められた意味
新入社員のシバです。 今日は、お仏壇にお供えするうえでとても大切な「三大供養(さんだいくよう)」についてお話します。これは“お仏壇での基本中の基本”とも言われるもので、「花・香・灯」の3つを指します。この3つは「三具足(さんぐそく)」と呼ばれる仏具、『花立(はなたて)、香炉(こうろ)、火立(ひたて)』を使ってお供えします。 まず「花」は、仏様の慈愛や忍耐を象徴しています。やがて枯れていく花の姿は「諸行無常(しょぎょうむじょう)」。すべてのものは移ろう、という仏の教えを私たちに伝えてくれます。季節の花をお供えすることで、日々の感謝や祈りの気持ちも自然とあらわれます。 次に「香」。お香の香りには、心を静めて落ち着かせる力があると言われています。仏様の智慧を表し、香りが部屋の空気だけでなく、私たちの心まで清めてくれるように感じます。短い時間でも、お線香をあげると気持ちがすっと整いますよね。 そして「灯」。ロウソクの明かりは、仏様の智慧の光を象徴しています。暗闇を照らすように、迷いや不安を取り除き、正しい道へ導いてくれるとされています。静かに灯を見つめて
2025年11月10日


仏壇に供える枯れない花「常花」に込められた意味
新入社員のシバです。今日は「常花(じょうか)」についてご紹介します。仏壇や祭壇に飾られている、金色の蓮の花のような造花を見たことはありますか? あれが常花です。 常花は、生花のように枯れることがないため「永遠に咲き続ける花」といわれます。仏様への感謝と敬意を表すためにお供えされる、とても大切な仏具です。 仏教において蓮の花は特別な存在です。泥の中から生えても、その泥に染まらず清らかな花を咲かせる姿は、どんな環境でも心を汚さず悟りを開く仏様の教えを象徴しています。まさに「清らかさ」と「強さ」を合わせ持つ花なんですね。 仏壇は、極楽浄土を表すものといわれています。そこに常花を飾ることで、その世界をより美しく荘厳にします。特に金色の常花は、最高の蓮の花をかたどったものとして、お供えにふさわしいとされています。枯れることのない常花は「常住不変」、つまり仏法が永遠であることをあらわしているのだそうです。 また、常花は仏花とは別のもので、基本的に左右一対で飾ります。茎の本数は3本、5本、7本など奇数でつくられるのが一般的です。咲いている花は「現在」、つぼみは
2025年11月3日


数珠の「略式念珠」と「本連念珠」はどう違うの?
新入社員のシバです。今回はお客様からもよくご質問をいただく「略式念珠(りゃくしきねんじゅ)」と「本連念珠(ほんれんねんじゅ)」の違いについて、私なりに整理してみました。 まず大きな違いは、“珠(たま)の数”と“宗派の違い”にあります。 本連念珠は、宗派ごとに正式な形や作法が定められており、たとえば浄土宗や真言宗などでは珠の並び方や房の形にも特徴があります。一方の略式念珠は、宗派を問わずどなたでも使えるように簡略化された形で、葬儀や法要など幅広い場面で用いられています。 珠の数も異なります。正式な本連念珠は、108個の珠を基本とし、二重(ふたえ)になっているものが多いのが特徴です。これに対して略式念珠は、108個を簡略化して22玉や20玉、あるいはその半分の54玉などで作られており、一重(ひとえ)で仕立てられることが一般的です。ただし、宗派や地域によって形や数の違いがあるため、「一重=略式」「二重=本連」とは限らない場合もあります。 価格面では、略式念珠の方が比較的お手頃なものが多く、初めての方にも選ばれやすい傾向があります。本連念珠は、素材や作り
2025年10月21日
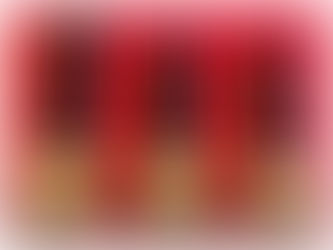

白木位牌から本位牌へ。四十九日までの準備
新入社員のシバです。今日は「位牌(いはい)」について、私が学んだことをまとめてみます。お客様からもよくご質問をいただく内容で、私自身も入社して初めて知ったことが多いので、同じように疑問を持っておられる方に参考になれば嬉しいです。 まず、葬儀のときに使うのは「白木位牌(仮位牌)」というもので、これはあくまで仮のものなんです。本番の「本位牌」は、四十九日までに用意するのが一般的です。四十九日の法要の際には、僧侶さまに開眼供養(魂入れ)をしていただき、白木位牌から本位牌へ魂を移すことで役目が引き継がれます。 ここで気をつけたいのが、本位牌の準備に少し時間がかかるという点です。 戒名などの文字入れに通常2~3週間ほどかかりますので、余裕を持って仏壇店へご依頼いただくことが大切です。実際に、法要直前に慌てて駆け込まれる方も少なくないそうで…。私も先輩から「早めのご相談が安心につながるよ」と教わりました。 また、宗派によっては少し違いがあることも学びました。 たとえば浄土真宗では、故人は亡くなるとすぐに仏になるという教えに基づき、原則として位牌は用いません。
2025年9月27日


お盆提灯をきれいに長持ちさせる出し方・しまい方のコツ
新入社員のシバです。お盆の時期になると、ご先祖さまを迎える大切な役割を担うお提灯。毎年出すものだからこそ、出し方や片付け方を丁寧にすることで、見た目の美しさや耐久性がぐっと変わってきます。今回は、意外と悩まれる方が多い「お提灯の出し方としまい方」のポイントをご紹介します。...
2025年8月10日


自然界の提灯 ほおずきの不思議な役割
新入社員のシバです。日ごとに暑さが増してきて、いよいよお盆が近づいているなあと感じています。お盆といえば、提灯や迎え火を思い浮かべる方も多いと思いますが、今回は「ほおずき」についてご紹介します。 ほおずきは、鮮やかなオレンジ色とふっくらとした形が特徴の植物です。昔からお盆の...
2025年7月1日


お盆の提灯に家紋を入れる理由、知っていますか?
はじめまして。新入社員のシバです。毎日先輩に教わりながら仏壇・仏具の世界の奥深さを学んでいます。 さて、あと数ヶ月でお盆がやって来ますね。お盆と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、ご先祖さまを迎える提灯という方も多いはず。先日、お客さまから「どうして提灯に家紋を入れるの?」とご質...
2025年5月16日
展示替え品や、店舗の奥で眠っていた良質な仏具を、メルカリ『良品仏壇』にてご案内しております。品質は折り紙付き。ご縁があれば大変お買い得な一品です。
お友達のご登録者さま限定のプレゼントや、田渕仏心堂の店舗で使用できる割引クーポンを配信中です。また、店舗に関するリアルタイム情報や仏事に関する豆知識なども配信しています。是非ご登録ください。
bottom of page

